まず、リハビリテーションとは、病気やケガで失われた機能を回復させるための治療です。
目的は、日常生活をできる限り自立して送れるようにすることにあります。
特に、沖縄で脳卒中後の退院後リハビリを検討している方にとっても、非常に重要です。
なお、その過程は、大きく分けて「急性期」「回復期」「維持期」の3つに分類されます。
急性期 | 沖縄で脳卒中後退院後のリハビリ

次に、急性期リハビリテーションについて説明します。
これは、脳卒中や骨折、手術などのあと、数日〜数週間の間に行うリハビリです。
この時期は、病気やけがの急性期にあたります。治療と並行して、機能回復や寝たきりの予防を目的としています。
急性期リハビリテーションの目的
急性期とは、発症や受傷から数日〜数週間の間にある、不安定な時期のことです。
また、この時期に行うリハビリの目的は、回復へ向けた土台づくりです。
- 安静による筋力・関節機能の低下を最小限に抑えるため、早期から安全に身体を動かす介入を行います。
- 肺炎や血栓症などの二次的な合併症を予防し、生命を守る支援もリハビリの大きな目的です。
- 将来の生活再建に向けて、早期からの離床や基本動作の再獲得を目指します。
特徴
急性期リハビリには、他の時期とは異なる、いくつかの重要な特徴があります。
- 病状が安定していない中で行うため、常に医師の指示のもと、全身状態を厳密に確認しながら実施されます。
→ そのため、リハビリの開始時期や内容は、医療チームの判断により柔軟に調整されます。 - ベッド上や車椅子での対応が中心となるため、ポジショニングや関節拘縮予防など、受動的なケアも含まれます。
- 発症直後から適切な刺激を与えることで、その後の回復を促進する効果が期待できます。
→ 実際、早期介入により退院後の自立度が高まるという報告も多く見られます。
行われること
- 急性期では、病状が安定していない状態でも、できる範囲でのリハビリが行われます。
- 具体的には、以下のような内容が含まれます。
- 運動療法:筋力の維持・向上や関節の可動域を広げる訓練、さらに歩行練習などを実施します。
- 機能訓練:食事・着替え・トイレなど、日常生活に欠かせない動作の練習を行います。
- 言語療法:言葉の理解や発話に関するトレーニングを通して、コミュニケーションの改善を図ります。
- 嚥下訓練:飲み込む力の維持・向上を目的とした訓練を行い、誤嚥性肺炎の予防につなげます。
- 認知機能訓練:記憶力や注意力、判断力などを高めるための訓練を行います。
- このように、多角的なリハビリを早期から取り入れることで、回復への準備を整えていきます。
急性期リハビリテーションのメリット
- 急性期にリハビリを導入することには、次のような大きな利点があります。
- 早期介入により、機能回復を促進できる
→ 病状が安定していなくても、適切なタイミングでリハビリを始めることで、その後の回復がスムーズになります。 - 合併症の予防につながる
→ たとえば、寝たきりによる肺炎や血栓、褥瘡(じょくそう)などのリスクを減らすことができます。 - 社会復帰の準備が早く整う
→ できるだけ早く日常生活に戻れるよう支援するため、結果としてQOL(生活の質)の向上も期待できます。
回復期 | 沖縄で脳卒中後退院後のリハビリ

急性期を過ぎ、比較的安定した状態になった時期。そして、最も積極的にリハビリを行い、失われた機能の回復を促します。
回復期の目的
- 運動・感覚・認知などの機能回復を促し、ADL(日常生活動作)の改善を目指します。
- 床ずれや肺炎などの合併症を防ぎ、さらに健康状態の維持・改善を図ります。
- 将来的な社会復帰を見据え、仕事や家庭への復帰準備を行います。
特徴
- 物理療法、作業療法、言語療法など、様々な種類のリハビリを組み合わせ、集中的に行います。
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが、患者さんの状態に合わせて個別のプログラムを作成し、指導を行います。
- 医師、看護師、栄養士など、多職種が連携して治療にあたります。
回復期リハビリテーションでおこなわれること
- 運動療法: 筋力トレーニング、関節の可動域訓練、加えて歩行訓練なども行います
- 作業療法: 日常生活動作訓練(食事、着替え、トイレなど)、高次脳機能訓練など
- 言語療法: 言語障害の改善、コミュニケーション能力の向上
- 心理療法: ストレス管理、心のケア
回復期リハビリテーションのメリット
- 集中的なリハビリにより、より短期間で機能回復が期待できます。
- 合併症のリスクを減らし、健康状態の改善に繋がります。
- 早期に社会復帰を目指せるよう、必要な支援を受けることができます。
- 身体機能の回復だけでなく、精神的な安定も図ることができます。
維持期 | 沖縄で脳卒中後退院後のリハビリ

維持期とは、症状が落ち着いた後の時期を指します。
病気やけがの回復を目指す急性期・回復期を経て、日常生活に戻った段階です。
この時期に行われるリハビリを「維持期リハビリ」または「生活期リハビリ」と呼びます。
維持期リハビリテーションの目的
- さらに機能を向上させ、より快適な生活を送れるようにすることを目指します。
- 単に身体機能だけでなく、精神的な面も考慮し、生活の質を向上させることを目的とします。
特徴
- 患者さんの状態や目標に合わせて、一人ひとりに合ったプログラムを作成します。
- 長期的な視点で、継続して取り組むことが重要です。
- 患者さん自身が積極的にリハビリに参加することが大切です。また、目標達成に向けて努力する姿勢が求められます。
- そしてリハビリテーションで得た能力を、日常生活に活かせるように指導します。
維持期リハビリテーションの重要性
維持期リハビリは、獲得した機能を維持し、生活の質を保つために重要です。
また、脳卒中や脊髄損傷のように後遺症が残る疾患では、長期的な支援が必要です。
退院後に自費リハビリを選ぶメリット| 沖縄で脳卒中後退院後のリハビリ

退院後(維持期)に自費リハビリテーションを行うことは、回復期のリハビリテーションをさらに発展させ、より高いQOL(Quality of Life)を目指す上で非常に有効な手段です。
維持期における自費リハビリテーションのメリット
- 保険診療のリハビリテーションでは、限られた時間や回数の中で治療を行う必要があります。
自費リハビリテーションでは、個人の目標や状態に合わせて、より柔軟なプログラムを組むことができます。
例えば、特定の動作の改善に特化したり、趣味の活動を取り入れたり、運動強度を調整したりといったことが可能です。 - 自費リハビリテーション施設では、より専門性の高い施術を受けることができます。例えば、マニュアルセラピー、運動療法、体幹トレーニング、呼吸トレーニングなど、多岐にわたる施術の中から、自分に合ったものを選択できます。
- 回数や期間の制限がなく、継続してリハビリテーションを受けることができるため、症状の悪化を防ぎ、獲得した機能を維持することができます。また、定期的な評価を行いながら、プログラムを修正していくことも可能です。
- 自分の意思でリハビリテーションを選択し、費用を負担することで、より主体的に取り組むことができます。療法士との連携を密にすることで、モチベーションを維持し、目標達成に向けて努力することができます。
維持期における自費リハビリテーションの具体的なメリット例
- 日常生活動作の改善:歩行、階段昇降、食事、着替えなど、日常生活動作のさらなる改善を目指せます。
- 運動能力の向上:筋力、柔軟性、バランス能力の向上により、よりアクティブな生活を送ることができます。
- 痛みの軽減:痛みを伴う動きに対する不安を解消し、活動範囲を広げることができます。
- 精神的な安定:リハビリテーションを通して自信を取り戻し、QOLの向上に繋がります。
まとめ
リハビリテーションの開始時期には急性期・回復期・維持期があり、それぞれの時期に合ったリハビリテーションをしていく必要があります。
維持期における自費リハビリテーションは保険診療では得られない、より高度なリハビリテーションを受けることができるというメリットがあります。沖縄リハビリステーションNOVAが実施している自費リハビリは退院後の患者一人ひとりの状態や生活背景を踏まえ、目標を設定した上でマンツーマンでのリハビリを提供してくれるため、多くの対象者に高く評価されている話題のサービスです。沖縄リハビリステーション NOVAではご相談なども承っていますので、気軽にご相談ください。維持期のリハビリを検討している方は是非、自費リハビリを導入している沖縄リハビリステーションNOVAに相談してみてはいかがでしょうか。
-1-1-1024x341.jpg)
【画像をクリックすると詳細確認とお申し込みができます】
\\YouTubeで情報発信もしています//

【画像をクリックするとYouTubeを見ることができます↑】




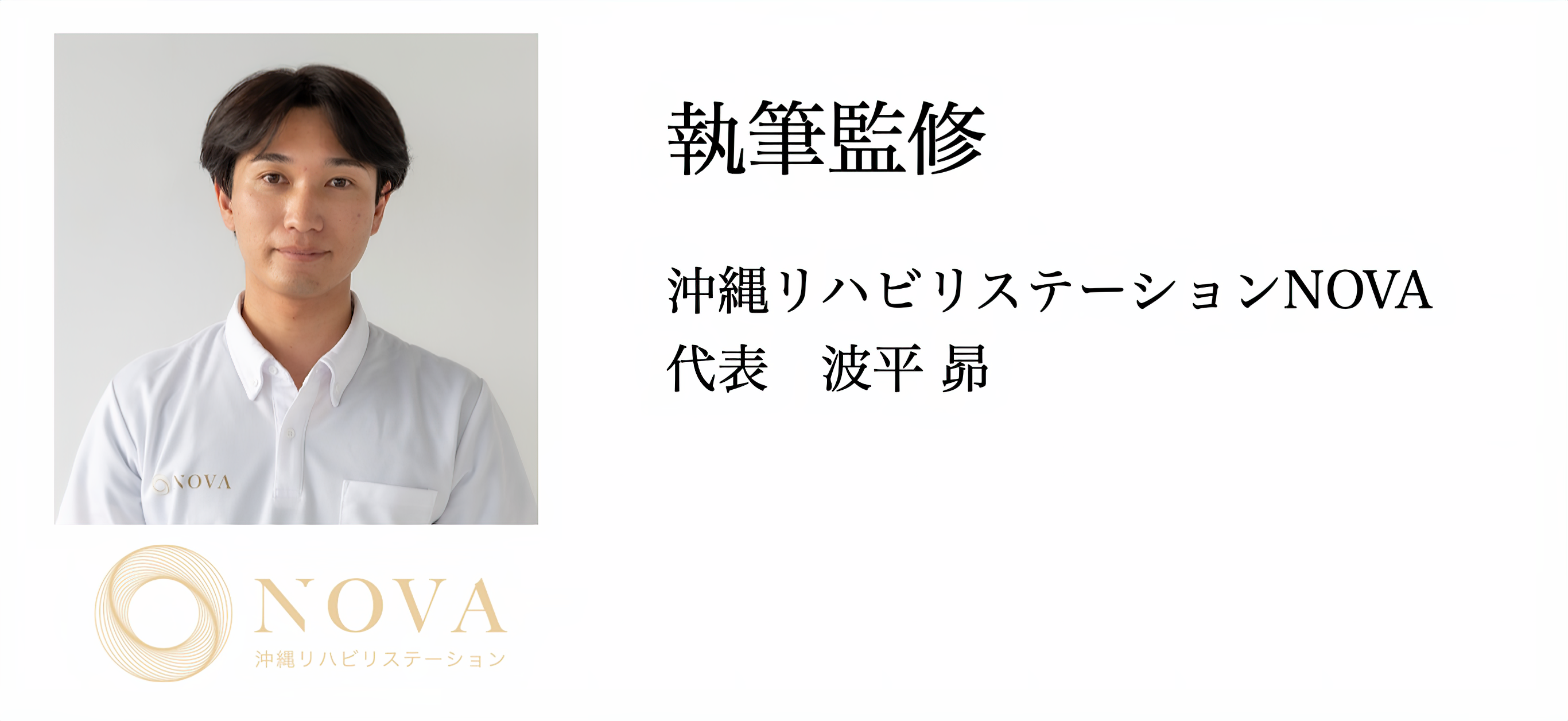
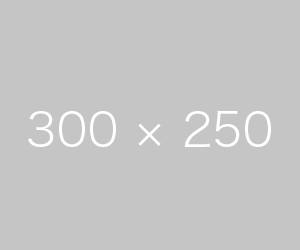
コメント