理学療法と作業療法の違いについて、どちらもリハビリテーションに関わる専門職です。
そして、それぞれ得意とする分野が異なります。

まず、理学療法(Physical Therapy、PT)は、「動く力」を取り戻すための専門的なリハビリです。
歩けない、関節が動かないなどの症状に対して、体の機能に直接アプローチします。
運動機能の回復・維持を目的としています。
具体的には、運動、温熱、電気、水、光線などの物理的な手段を用いて、身体の機能改善を図ります。
たとえば、こんなときに理学療法が必要です:
加齢や運動不足で筋力やバランスが低下している
→転倒予防のトレーニングを行う。そして、自立した生活をサポートします。
手術や骨折後に足がうまく動かない、または歩けない
→筋力トレーニングや歩行練習で「動ける体」に戻します。
脳卒中後、片麻痺で体が思うように動かない
→動かし方の再学習を行い、麻痺側の機能を引き出していきます。
腰痛や膝痛で動くと痛い
→痛みの原因を見極め、姿勢や歩き方の改善、そして体の使い方を修正します。
理学療法では、主に以下のような効果が期待されます。
- 関節の動きを改善する
関節が硬くなっている場合、ストレッチやモビライゼーション(徒手的な関節操作)を行い、動かしやすさを取り戻します。
- 筋力の向上
低下した筋力に対して、トレーニングを通じて力をつけ、立つ・歩くなどの日常動作を安定させます。
- 歩行や動作の再獲得
正しい歩き方や立ち上がり方を練習し、そして生活に必要な移動能力を改善します。
- バランス能力の改善
転倒のリスクを減らし、屋外や段差のある環境でも安全に動けるように訓練します。
- 痛みの軽減と姿勢改善
関節や筋肉のアンバランスを整えることで、慢性的な痛みや猫背・反り腰といった姿勢不良の改善が期待されます。
流れは?
- 初回評価(問診)
生活背景や現在の症状、そして今困っている動作などを丁寧に聞き取ります。 - 身体機能の測定
関節の可動域、筋力、バランス能力、それに加えて歩行の状態などを評価します。 - リハビリ計画の立案
目標に合わせて、最適なトレーニングやアプローチ方法を決めます。 - 治療の実施
筋力トレーニング、ストレッチ、歩行練習、電気刺激療法などを個別に実施します。 - 再評価と調整
一定期間ごとに効果を確認し、必要に応じて内容を見直していきます。
理学療法の治療法
- 運動療法: 患者さんの状態に合わせた基本的な運動を行います。
- 物理療法: 熱、電気、超音波などの物理的なエネルギーを用いて、痛みを軽減したり、筋肉をリラックスさせたりします。
- 手技療法: マッサージや関節モビライゼーションなど、手技を用いて身体の機能を改善します。
理学療法を受けるには?
医師の診断に基づき、理学療法士による治療を受けることができます。また、整形外科、神経内科、リハビリテーション科など、様々な診療科で理学療法を受けることができます。
作業療法

次に作業療法(Occupational Therapy、OT) は、日常生活の作業を通じて、心と体の機能回復を目指すリハビリです。
食事・着替え・入浴などの生活動作や、家事・仕事・学習といった役割の支援
また、趣味や余暇活動の再開やメンタルケアも対象になります。
なぜ作業療法が必要なの?
脳卒中や脊髄損傷、骨折、関節の病気など、対象は多岐にわたります。
そして、精神疾患や発達障害、高齢による体力低下にも対応し、「その人らしい生活」を支える支援が必要です。
何が期待できる?
- 食事、着替え、トイレなど、日常生活に必要な動作がスムーズに行えるようになります。
- また、家事、仕事、ボランティア活動など、社会生活への参加を促します。
- 趣味や余暇活動を楽しむことで、心の安定や充実感を得られます。
- コミュニケーション能力の向上やストレス管理などを支援します。
流れは?
- アセスメント: 特に、患者さんの生活背景や困りごと、目標などを詳しく聞き取り、現在の能力を評価します。
- 治療計画の立案: 患者さんの目標や評価結果に基づいて、個別的な治療計画を作成します。
- 治療の実施: 具体的な作業を通して、目標達成を目指します。
- 効果の評価: 定期的に評価を行い、治療計画を見直します。
作業療法の治療法
- 日常生活動作訓練: 食事、着替え、入浴などの練習を行います。
- 高次脳機能訓練: 記憶力、注意力、判断力などの訓練を行います。
- 社会参加訓練: 家事、仕事、ボランティア活動などの練習を行います。
- レクリエーション活動: 趣味や余暇活動を通して、心身のリラックスを促します。
作業療法を受けるには?
医師の診断に基づき、作業療法士による治療を受けることができます。
そして、病院、リハビリテーション施設、地域包括支援センターなど、様々な場所で作業療法を受けることができます。
理学療法と作業療法の違いの比較

対象者
- 理学療法: 身体に障害のある人、または障害の発生が予測される人が主な対象者です。
加えて運動機能や身体機能の回復・維持・改善を目的としています。 - 作業療法: 身体や精神に障害のある人、またはその可能性のある人が主な対象者です。
日常生活動作や社会生活に必要な能力の回復・維持・改善を目的としています。
療法の内容
- 理学療法は、身体を動かす力や動きの質を高めるリハビリです。
その上、筋力や柔軟性、バランス感覚などを改善し、日常動作をスムーズに行えるようサポートします。
主な手法には、筋力トレーニング、関節可動域訓練、歩行訓練、電気刺激や温熱療法などがあります。
- 作業療法は、「生活の中の作業」を通して、心と体の働きを整えるリハビリです。
そして、食事や入浴などの日常動作、家事や仕事、趣味や余暇の活動を再び行えるよう支援します。
精神面のサポートも含まれ、社会復帰や生活の質の向上を目指します。
効果
- 理学療法: 運動機能や身体機能の改善、疼痛の軽減、呼吸循環機能の改善、障害予防などが期待できます。
- 作業療法: 日常生活動作の自立、社会参加の促進、生活の質の向上、精神的な安定などが期待できます。
一般の方に説明する場合
理学療法士(PT)は基本的な動作(立つ、座る、歩くなど)ができるように、体の機能を回復させる専門家です。運動やマッサージ、電気治療などで、体の痛みを和らげたり、筋力をつけたりします。
例として、「骨折して足が動かしにくくなった人が、また歩けるようにサポートする」、「スポーツでケガをした人が、また運動ができるようにリハビリをする」のが理学療法士です。
作業療法士(OT)は日常生活(食事、着替え、入浴など)や社会生活(勉強、仕事、遊びなど)ができるように、生活に必要な動作をサポートする専門家です。手芸や工作、ゲームなど、様々な活動を通して、心と体の機能を回復させます。
例えば、「手が不自由な人が、ボタンを留めたり、字を書いたりできるように練習する」
「病気で学校に行けなくなった人が、また学校に通えるように、生活リズムを整えたり、勉強をサポートする」
それが作業療法士です。
つまり、理学療法士は体の土台を作る人、建物で言えば、基礎や柱を作るイメージです。
そして、作業療法士は生活の道具を作る人、建物で言えば、家具や電気など、生活に必要なものを作るイメージです。
理学療法で体の基本的な機能を回復させ、作業療法で日常生活や社会生活を送るための応用的な機能を回復させます。
また、両方が協力して、患者さん一人ひとりの目標に合わせて、最適なリハビリテーションを提供しています。
まとめ

今回は理学療法と作業療法の違いは?を解説してきました。理学療法と作業療法の違いは対象者や療法の内容、効果の違いなどがあります。
沖縄リハビリステーション NOVAでは、自費リハビリテーションを実施しており、ご相談なども承っていますので、気軽にご相談ください。
また、退院後のリハビリを検討している方は是非、NOVAに相談してみてはいかがでしょうか。
-1-1-1024x341.jpg)
【画像をクリックすると詳細確認とお申し込みができます】
\\YouTubeで情報発信もしています//

【画像をクリックするとYouTubeを見ることができます↑】




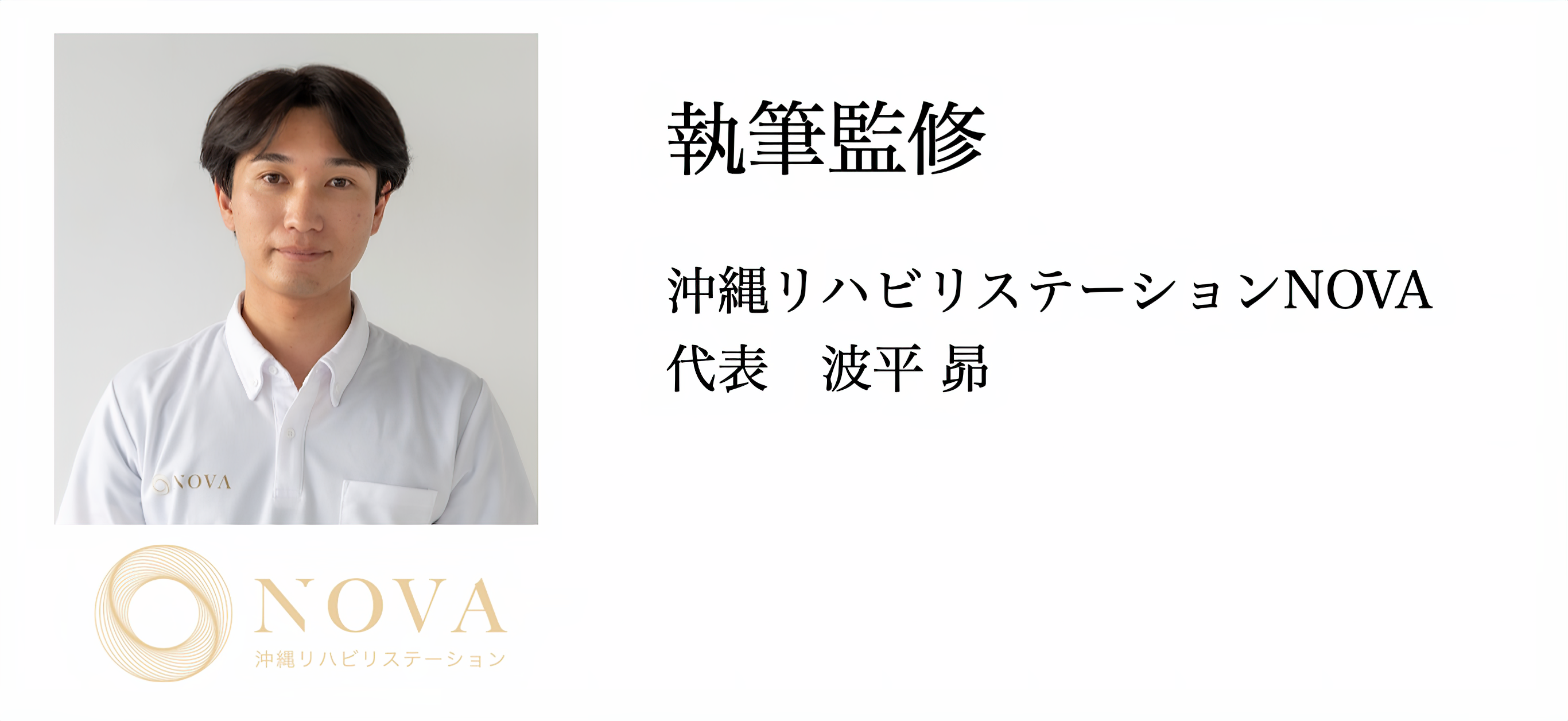
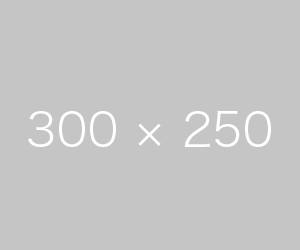
コメント