【1】クロートゥ(内反尖足)とは? 沖縄でできるリハビリ場所は?

クロートゥ(内反尖足)のリハビリでお悩みの方へ。沖縄では、脳卒中後や麻痺後に適したリハビリ施設がまだ限られており、症状の悪化や転倒につながるケースもあります。
放置はとても危険です。
転倒リスクが高まり、歩くことへの恐怖が増していきます。
その結果、外出が減り、生活の幅が狭くなってしまいます。
クロートゥは一度起こると自然に治ることは少なく、放置することで変形が進んでしまうこともあります。
沖縄でクロートゥ(内反尖足)のリハビリを受けられる場所を探している方は少なくありません。
そのため、症状に気づいた段階で早期に対応することがとても大切です。
【2】クロートゥ(内反尖足)の原因と症状|脳卒中後の特徴と沖縄でのリハビリ

◎ 原因:脳梗塞・脳出血などの脳卒中
脳卒中の後には、麻痺や筋緊張の変化がよく見られます。
その影響で、足の指や足首の筋肉のバランスが崩れます。
特定の筋肉が過剰に働いてしまうことで、指が曲がったり、つま先が伸びきってしまう「内反尖足」が起こります。
さらに、脳から筋肉への指令がうまく届かなくなることで、協調運動が難しくなります。
その結果、足の形や歩き方が不自然になることもあります。
◎ よく見られる症状
- 足の指が曲がったままで伸ばせない(クロートゥ)
- つま先が地面に引っかかる(内反尖足)
- 歩き出しが不安定になる
- 靴が合わない、履けない
- つま先から接地するため、踵が着地しづらい
これらの症状は、歩きにくさや転倒だけでなく、腰や膝、股関節への負担にもつながります。
【3】放置してはいけないクロートゥの影響

クロートゥは単なる「足の形の問題」ではありません。
- 歩行の安定性の低下:地面に引っかかりやすくなり転倒のリスクが高まる
- 身体全体の姿勢に影響:足部の異常は膝・腰・背中の痛みにもつながる
- 外出や活動量の減少:怖さから外に出なくなり、フレイルやうつにもつながる
- 家族の負担増加:介助量が増え、精神的・身体的な負担になることも
だからこそ、早期の評価とリハビリがとても大切です。
クロートゥを放置すると、筋肉や関節の柔軟性が失われます。
その結果、後からリハビリをしても改善しにくくなることがあります。
また、足の変形が進むと、膝や股関節、骨盤などにも影響が及ぶことがあります。
できるだけ早い段階で対処することが大切です。
精神的にも影響があります。
歩くたびに引っかかる、つまずくなどの失敗体験が続くと、自信や意欲が下がってしまいます。
モチベーションの低下は、回復の妨げになり、生活の質(QOL)を下げることもあります。
【4】実際に行われているリハビリの例とストレッチ動画の紹介|クロートゥ リハビリ 沖縄
▶️ クロートゥに対するストレッチ動画は画像をクリック↑
クロートゥへのリハビリは、徒手によるアプローチだけでなく、利用者が自宅でも継続できるストレッチを併用することが重要です。
以下の動画では、クロートゥに対するストレッチ方法を分かりやすく紹介しています:
足指の筋緊張をやわらげ、歩行時のひっかかりを軽減する簡単な方法です。医療・リハビリ従事者の指導のもと、無理のない範囲で継続的に行うことが推奨されます。
このようなセルフケアを取り入れながら、リハビリ専門職による個別指導を併用すると、改善効果はさらに高まります。
また、リハビリでは、足の構造だけでなく、歩行時にどのように体重がかかるのか、どのように身体全体のバランスが取れているかを観察することが重要です。たとえば、かかとに荷重がかからず、常につま先立ちのような状態になっている場合、ふくらはぎの筋肉が過緊張になり、さらにクロートゥが悪化するリスクがあります。
最近のリハビリ施設では、動画分析やセンサーを用いた動作解析など、科学的な視点から歩行を評価する取り組みも進んでいます。こうした技術は、見た目だけでは分かりにくい微細な動作のズレやバランスの崩れを可視化し、より効果的なリハビリ戦略を立てるうえで役立ちます。
加えて、インソールや装具などの補助具の選定もリハビリの一環として重要です。足部の変形を補正し、正しい荷重パターンを誘導することで、歩行の安定性が高まり、転倒の予防につながります。
【5】クロートゥを防ぐためにできる生活習慣の見直し|沖縄 リハビリ

クロートゥの悪化を防ぐためには、日々の生活習慣の見直しも欠かせません。特に以下のポイントが重要です:
- 長時間同じ姿勢をとらない:麻痺側の足に負担がかかり続けることで筋緊張が高まりやすくなります。
- 適切な靴を選ぶ:つま先部分に余裕があり、足にフィットする靴を選ぶことで、変形の進行を防ぐ効果が期待できます。
- 定期的に足のチェックをする:皮膚の状態や爪の変形、筋肉の硬さを日常的に観察することで、変化に早く気づけます。
- 水分と栄養をしっかり取る:筋肉の柔軟性や神経伝達の正常化には、ビタミンやミネラルのバランスが欠かせません。
また、家族の方が適切にサポートできるよう、リハビリの専門職による指導を一緒に受けることもおすすめです。
【6】脳卒中後のリハビリはいつまで必要?|クロートゥ リハビリ 沖縄
「もう何年も経ったから、リハビリしても意味がないのでは?」と感じている方も少なくありません。しかし、脳卒中後の身体は常に変化しており、正しい刺激を与えることで改善する可能性はあります。
特にクロートゥのように筋緊張が関与する症状は、適切な介入によって機能改善が期待できる領域です。実際、数年経過した方でも、「歩きやすくなった」「靴が履きやすくなった」「転びにくくなった」といった変化を実感するケースがあります。
大切なのは、「今からでも遅くない」という意識で、一歩を踏み出すことです。
【7】まとめ|クロートゥに気づいたら、まずは行動を

クロートゥ(内反尖足)は、脳卒中後の代表的な後遺症の一つです。歩きにくさや転倒のリスクを高め、生活の質に大きな影響を与えます。
しかし、放置しないことで、進行を防ぎ、改善を目指すことも可能です。
- 歩行時に足が引っかかる
- 指が曲がって伸びない
- 靴が合わず履きにくい
そんな症状に気づいたら、ぜひリハビリの専門職に相談してみてください。
「今さら…」ではなく、「今から」始めることが大切です。
沖縄リハビリステーションNOVAも全力でご協力いたします。
【ホームページを見る→】https://nova-okinawa.jp/




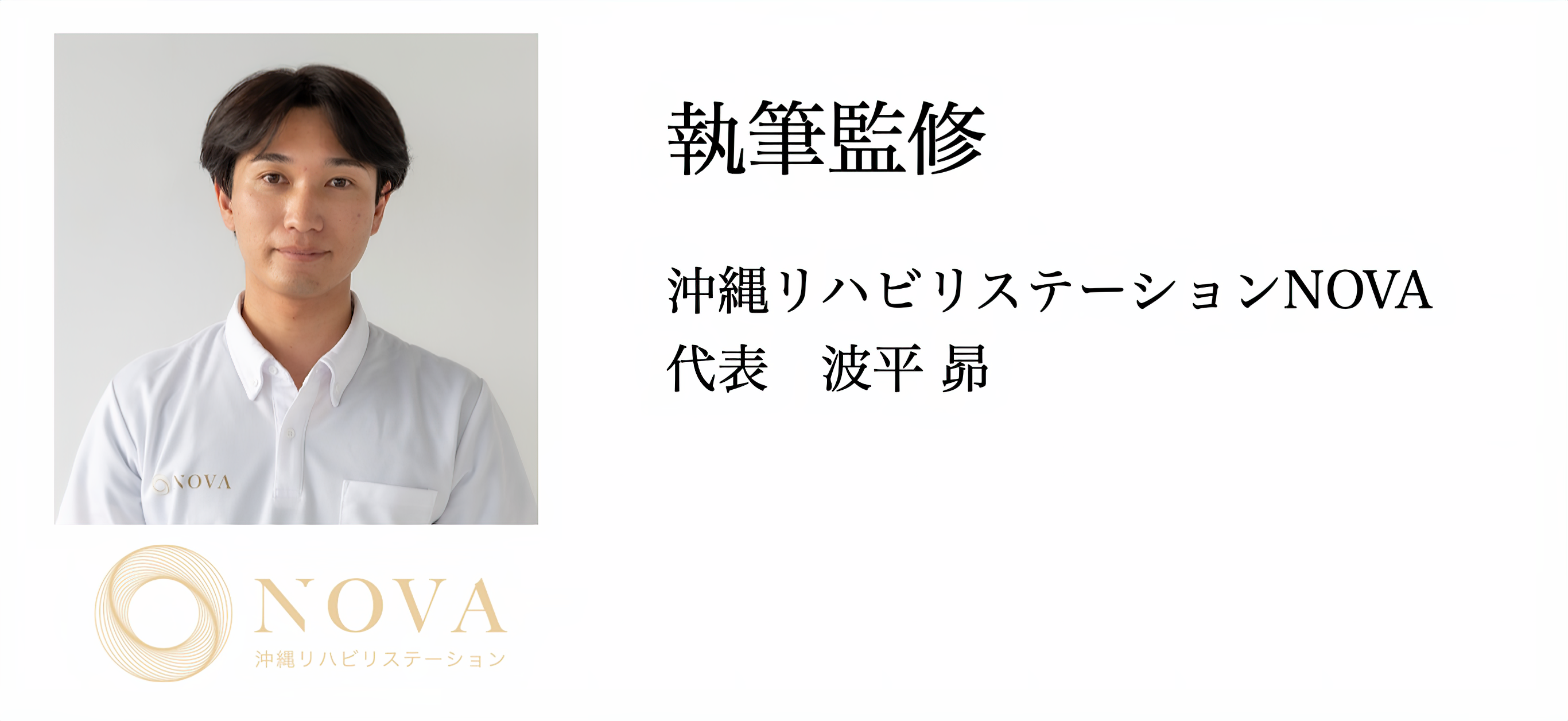
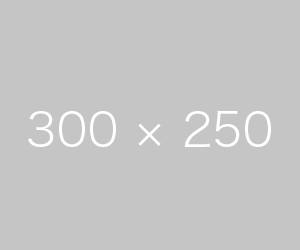
コメント